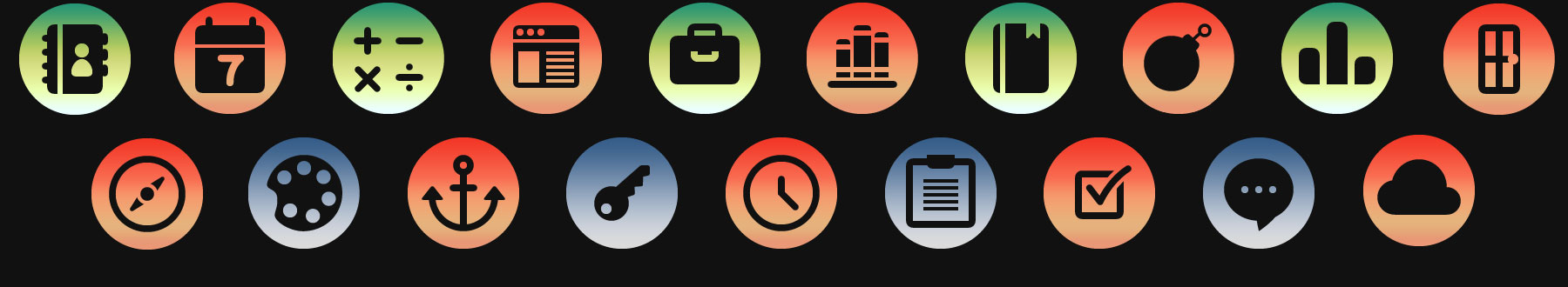痛みのメカニズム:侵害性ニューロンの役割とその特性
HPCニューロンとその応答特性
痛みの感覚は多様で複雑です。
Craigによると、HPCニューロンは低閾値機械刺激には反応しませんが、侵害性機械刺激や熱・冷刺激には応答します。
特に、HPCニューロンの一部は冷刺激(28.7°C~12.5°C)に反応し、15°C以下では反応が高まります。
この温度は、人間にとって痛みを伴う冷たさであり、その時点でHPCニューロンの活動が著しく増加します。
恒常性感覚路としてのHPCニューロン
痛みは単なる「はい・いいえ」のデジタル的な感覚ではありません。
第一次感覚神経の多モードC型侵害感覚器(polymodal C-nociceptor)や脊髄後角第I層中のHPCニューロンは、単純な侵害感覚経路というよりも、恒常性感覚路(homeostatic afferent pathway)として働いています。
これらのニューロンは、身体の恒常性を維持するための重要な情報を脳に送ります。
冷細胞の役割
第1層中の冷細胞(cool cell)は、正常皮膚温(約34°C)から応答し始め、15°Cで定常頻度に達します。
この温度は人間にとって痛みを伴う冷たさであり、そのときHPCニューロンの活動が高まります。
冷細胞は、冷たさの感覚を脳に伝える役割を果たし、これが痛みとして認識されるのです。
前脳での感覚チャネルの統合
熱性の苦しみや焼痛の知覚は、前脳でのこれらの感覚チャネルの統合によって決まります。
これは単純な侵害知覚というよりも、恒常的動機づけ(homeostatic motivation)に関与しています。
つまり、身体が適切な温度や状態を維持するための重要な役割を果たしているのです。
侵害性脊髄視床路ニューロンの応答
Andrewらの研究では、麻酔ネコの腰仙髄後角第1層にある2種の侵害性脊髄視床路(nociceptive spinothalamic tract (STT) neuron)が機械的刺激(0.1~5mm2の面積で、20g以下の重力)でどのような応答の差を示すかを調べています。
熱刺激に応じない侵害特殊ニューロン(NSN)は、熱・つまみ・冷刺激に応じる多モード侵害感覚器(HPC)よりも敏感であることが明らかになりました。
NSNとHPCの違い
NSNは機械的痛みに鋭く応じ、前脳に正確な痛みの場所を知らせます。
これに対して、HPCはC末梢神経からの入力を受けるため、より広範囲で多様な痛みの感覚に応答します。
これらの違いは、NSNが主にA末梢神経から情報を伝えるのに対し、HPCがC末梢神経から情報を伝えることに起因します。