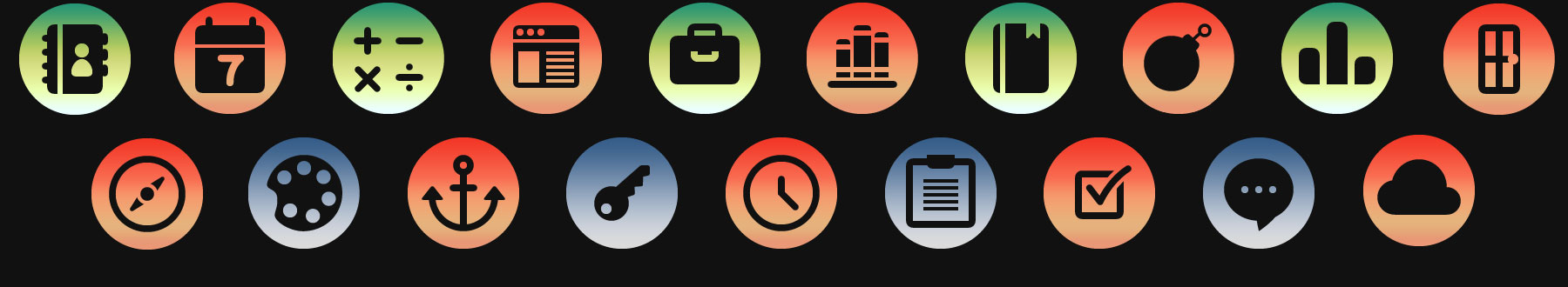関連痛のメカニズム:Capsaicinと痛覚過敏
1. 関連痛とは?
関連痛(referred pain)は、痛みの原因が内臓や骨格筋にあるにもかかわらず、皮膚など別の部位に痛みを感じる現象です。
これは、痛覚信号が脊髄後角第V層内の広作動域細胞(WDR細胞)に集約されるために起こります。
2. Capsaicin注射と痛覚反応
Capsaicinをヒトの皮内に注射すると、最初の3〜5分間は強い焼痛を感じます。
その後、約30分間にわたり、機械的な触刺激に対して異痛や痛覚過敏が生じます。
これは、痛覚と触覚の信号がWDR細胞に集約されるためです。
3. WDR細胞の役割
WDR細胞は、痛覚や触覚の信号を集約する役割を担っています。
これらの細胞は、皮膚からの痛覚信号だけでなく、内臓感覚信号や骨格筋痛感覚信号も受け取ります。
そのため、内臓や骨格筋に原因がある痛みが、皮膚の特定の部位に感じられるのです。
4. NSNとの違い
脊髄後角第1層の侵害特殊ニューロン(NSN)は、関連痛には関与しません。
NSNは主に侵害刺激に対して反応しますが、WDR細胞のように広範囲の感覚信号を集約する機能はありません。
そのため、関連痛のメカニズムにおいてはWDR細胞が中心的な役割を果たします。
まとめ
関連痛の現象は、WDR細胞がさまざまな感覚信号を集約することによって生じます。
Capsaicinの注射により生じる痛覚過敏も、この細胞の働きによるものです。
関連痛の理解は、痛みの治療や診断において重要な視点を提供します。
これにより、痛みの原因を正確に特定し、適切な治療を行うことが可能になります。